失業保険の給付期間が延長されるというただそれだけの理由で、入校しました。
私の場合、給付期間が90日だったのですが、公共職業訓練を受講することによって、修了までの給付が保証されることになります。
従って、私は、入校前の1ヶ月と訓練中の6ヶ月の合わせて7ヶ月分給付を受けることに成功しました。
3ヶ月コースの職業訓練も多数あったのですが、上記の理由で敢えて半年間を選びました。
4月下旬から開始のコースでした。
ハローワークの窓口に行くと詳しい説明を受けられ、いろいろなコースを提案してくれます。
訓練内容は?
Microsoft Officeの技能を身に付けることを目的としたコースでした。
半年間の職業訓練を通じて、以下の資格を取得することができました。
サーティファイ主催
・Word文書処理技能認定試験 2級
・Excel表計算処理技能認定試験 2級
・PowerPointプレゼンテーション技能認定試験 上級
・Accessビジネスデータベース技能認定試験 3級
・Webクリエイター能力認定試験 初級(※ホームページ作成の検定です)
上記は、サーティファイという機関が主催する検定です。
Officeの検定としては、MOS(マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト)のほうが認知度が高いようなのですが、
検定料が手頃であり(MOSの半額以下)、より実務的な内容である(MOSは暗記さえすればクリアできるらしい)との理由で、
私の通っていた訓練コースではサーティファイの検定を採用していました。
その他、受験は任意ですが国家資格であるITパスポートの授業や、履歴書の書き方のコツなどを教えてくれる授業もあり、なかなか盛り沢山の内容でした。
入校の試験は?
職業訓練校は、倍率が高くてなかなか入れないという話を聞きましたが、私のコースは逆に定員割れをしていました。
定員は20人ですが、2次募集までかけて、ギリギリ20人集まったという感じです。
田舎で交通の便もあまり良くない場所に立地していたせいかもしれません。
試験は面接のみでした。
一応スーツ着用でしたが、私が受けた1次募集で既に定員割れしていることがわかっていたので、あまり緊張もせずに面接を受け、合格しました。
面接では、必ず「なぜこの職業訓練を志望したのか」ということが質問されます。
職業訓練を実施する目的はあくまでもその先の就職にありますので、対応のコツとしては、
「○○の職に就きたいのですが、今の自分のスキルでは不十分なので、この職業訓練で力と自信を身につけたい」
というのが模範解答になると思います。
他には、「前職を辞めた理由」「Officeソフトについて、どの程度使ったことがあるか」「通学の手段は?」「様々な人たちと勉学を共にすることになるが、コミュニケーションには自信があるか」などを質問されました。
面接は10~15分程度で終わりました。
クラスメイトはどんな人たち?
全員失業者です。それは当たり前として、老若男女様々です。若い人から定年前の人まで、本当に様々です。
一般的な傾向として、Office系、事務系の訓練の場合、男女比が2:8とか、男性がクラスに一人ぼっちとか、女性の比率が圧倒的になりがちなのだそうです。
しかし、私のクラスは男女比が半々で、特に20~30代の若い男性が多かったです。
職員の人も、これはかなり珍しいケースだと言っていました。
でも、おかげでクラスの雰囲気が良く、なんだかんだでわいわいと楽しい毎日を過ごすことができました。イジメなんてもちろんありません。
授業はどんな感じ?
Word、Excel、PowerPoint、Access、Webクリエイターの授業が検定必須ということもあり、メインで進みます。
最初の一ヶ月くらいWordの授業を毎日行い、最終日に検定を受ける。それが終わったら次の一ヶ月間Excelをやり、最終日に試験という具合です。
各授業とも、前半はテキストを見ながら講師の先生が解説し、一緒に操作しながら覚えます。後半は、試験対策の問題集をひたすら解きます。
授業の進行は、正直、遅いです。
全員合格させることを目的としているので、習得の遅い人のペースに合わせて進むためです。
ファイルを開く閉じるの操作だけを3回くらい繰り返し練習させられたりします。
同じ過去問題を3回くらい解かされたりします。
少し慣れている人にとっては最初から少し退屈な授業内容、初めての人にとっても試験の直前あたりは少し退屈になりそうです。
9:10開始、12:00~12:50まで昼休み、16:00終了、その他1時間ごとに10分の休憩、というのが一日の流れです。
ちなみに、テキスト代、受験料は自己負担でした。
私の場合、テキスト約15冊で約25000円、受験料として計23000円、出費しました。
失業手当はもらえるけど。公共職業訓練にかかる3つの費用とは?
実際の雰囲気は?
老若男女様々な人たちが集まりますが、全員が失業者ということもあり、雰囲気はとてもゆるいです。講師の先生も優しく丁寧です。怒られたりなんてしません。
最初はやはり仲良くやっていけるかどうか不安でしたが、次第に慣れてきますし、普通にしていればなんとかなります。
私たちの場合、開始1ヶ月が経った頃、喫煙所で「授業がとにかく退屈で苦痛だー」と誰かが本音を漏らしたあたりから仲良くなり始め、休みの日にたまに集まってバーベキューをしたりもするようになりました。
修了間近になると、モラトリアム期間が終わってしまうことへの一抹の寂しさと就職への焦りを感じてくるようになります。
半年間も一緒に過ごし、就職という目的を共にした仲間ですから、不思議で特殊な連帯感というか仲間意識が芽生えます。
私は初めは、「別に誰とも仲良くしなくていいや。失業給付金だけ貰えればそれでいい」と思っていたのですが、親切なクラスメイトに囲まれて、とても良い時間を過ごすことができました。
最終日には、自主的に飲み会を企画し、ほぼ全員参加しました。
修了後も、年に一回くらいはみんなで集まって飲み会でもしようという話になっています。
他のクラスでも修了後に集まったり、気の合う人と連絡を取り合ったりするケースは多いようです。
余談ですが、修了後、一週間程度は、学校が終わってしまったという喪失感や就職への焦燥から、なんとなくブルーな気持ちになってしまう人が多いと講師の先生が言っていました。
就職の支援は?
直接的な就職の斡旋などはありません。
従って、求人雑誌やハローワークなどを利用して、各自、自分の力で就職活動を進めて行く必要があります。
しかし、訓練も毎日ありますし、両立してこなすのはなかなか気力と体力が必要です。
私のクラスでは、訓練終了時点で2人だけが、就職先が決まっている状況でした。
訓練が修了してから本活的に就職活動に動き出すという人が多かったです。

職業訓練期間中の就職活動ってどうすればいいの?
職業訓練修了後の過ごし方―私の周り3人の実例
転職は情報戦!「特化型求人サービス5選」で効率良く進めるべし
失業手当の給付について
職業訓練を受講するにあたって最も重要なのが、失業手当の給付でしょう。
欠席すると、基本的にその日は失業手当が出ません。
但し、風邪をひいたなどの場合は、病院の診察を受け、領収書を提示すれば、その日のみは欠席でも手当を受け取ることができます。
病院に行ったという証明がない場合、体調が悪かったが病院に行かなかったという場合は、手当を受け取ることができませんので注意が必要です。
逆に言えば、具合が悪くなくても病院に行きさえすれば、手当を貰いつつ正々堂々と休むことができます。
日曜、祝日など、訓練がない日も手当は出ますが、休日を欠席で挟んでしまうと休日分は支給されなくなってしまいます。
例えば、「金曜日欠席、土休講、日休講、月祝日休講、火曜日欠席」としてしまうと、欠席した金曜日、翌火曜日だけでなく、それに挟まれた土日月分も支給対象外になってしまうということです。
葬式、結婚式への出席は、親族のもののみが給付対象です。
どの程度近しい親族までのものが給付対象になるかについては、事務的に厳密に定められていますので、予定のある方は確認しておきましょう。
遅刻早退については、給付の減額などの措置はないようです。
極端な話、1時間でも出席すれば、その日は全額支給されます。
職業訓練中に、アルバイトなどをすることは明確に禁止されています。
もし、単発のアルバイトや手伝いなどをして収入を得た場合、きちんと申請する必要があります。
その収入を得た日は、支給対象外となります。
終わりに感想
訓練期間中の半年間は、私にとって、ストレスから開放され、かつ、生活のリズムも作られるといった意味で素晴らしい半年間となりました。
学校に行って、座って授業さえ聞いていれば失業保険も出ますから、ある程度は、お金の心配も要りません。
ちなみに私は、訓練期間中の失業手当をコツコツと貯金していましたので、修了後も、しばらくは不安なく過ごせそうです。
職業訓練はなかなか知られていない割に、失業者にとっても、これから何かを学びたい人にとっても、すごく役立つ制度ですので、是非活用することをおすすめします。
参考記事:
・職業訓練の超絶メリット5つ!修了したので解説していきます
・公共職業訓練にデメリットはある? 私が感じた3つの短所

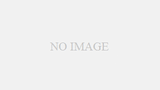
コメント
「失業保険の給付期間が延長されるというただそれだけの理由で、入校しました。」
この文章を読んで、思わずコメントしてしまいました。
職業訓練での給付金というものが、税金から支払われていることをご存知でしょうか。
失業保険を余分にもらえるいい方法があるよ、みたいに受け取られかねない記事を見て悲しい思いをしました。
失業給付を余分にもらえるいい方法があるかのような記事で、実際にはもらえないなら悲しいですが、実際に、失業給付を余分にもらえるいい方法なので、いい記事だと思いますよ。
失業保険の財源は、国庫負担と事業者と被保険者の負担がおよそ1/3ずつです。